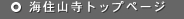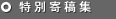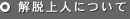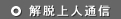海住山寺トップページへ
- 解脱上人特集
- 解脱上人について
解脱上人について

解脱上人貞慶 (1155年〜1213年) 左少弁藤原貞憲の子で、幼くして興福寺に入り、覚憲に師事してひたすら研学につとめ、維摩会・最勝会の講師までも歴任した南都仏教界随一の学僧であり、身をつつしむこときびしく、壮年に至り感ずる所あって笠置山にかくれ、名利をのがれてもっぱら徳をつまれた方でありましたが、晩年その心境が一そうひらかれるにつれて、人々を教化して仏道にむかわしめるために、この海住山寺に移り住まれたのでありました。
解脱上人年表| 年 | 月 | 出来事 |
| 1 久寿2年 1155 | 5月21日 | 誕生。父は藤原貞憲。祖父は藤原通憲(信西)。 叔父に覚憲・澄憲・勝賢らがいる。 |
|---|---|---|
| 8 応保2年 1162 | 南都に下向。 | |
| 11 永万1年 1165 | 出家受戒。 | |
| 18 承安2年 1172 | 醍醐寺の運阿闇梨について求聞持法を受ける。 | |
| 26 治承4年 1180 | 南都焼打ち。東大寺と興福寺の伽藍の大半が焼失する。 | |
| 28 寿永1年 1182 | 興福寺維摩会で研学竪義をつとめる。 |
|
| 11月27日 | 兜率天上生を発願し、『大般若経』書写を決意する。 | |
| 29 寿永2年 1183 | 7月 | 法勝寺御八講に聴衆として参加する。 |
| 30 元暦1年 1184 | 法勝寺御八講に聴衆として参加する。 | |
| 32 文治2年 1186 | 興福寺維摩会で講師をつとめる。 |
|
| 33 文治3年 1187 | 7月 | 法勝寺御八講で講師をつとめる。 |
| 35 文治5年 1189 | 5月 | 最勝講で講師をつとめる。 |
| 12月 | 法成寺御八講で竪義をつとめる。 |
|
| 36 建久1年 1190 | 最勝講で講師をつとめる。 |
|
| 7月 | 法勝寺御八講で講師をつとめる。 |
|
| 37 建久2年 1191 | 2月 | 2 法成寺御八講で講師をつとめる。「説法珍重。只恨其音少。」(玉葉) |
| 5月22日 | 興福寺南円堂の誦経の導師をつとめる。「表白甚優也。」(玉葉) |
|
| 10月11日 | 九条兼実の仏事の導師をつとめる。「殆可謂神歟」(玉葉) |
|
| 38 建久3年 1192 | 2月8日 | 笠置寺に籠居する旨を九条兼実に告げる。 九条兼実、思い止まるよう説得する。 |
| 7月20日 | 「発心講式」を著す。 |
|
| 39 建久4年 1193 | 秋 | 興福寺から笠置寺に移る。 |
| 41 建久6年 1195 | 7月24・25日 | 笠置寺で『大般若経』理趣分を書写する。(『大般若経』書写完了) |
| 11月19日 | 笠置寺に般若台を建立し、『大般若経』を安置する |
|
| 42 建久7年 1196 | 2月10日 | 専心の勧めで「弥勒講式」を著す。 |
| 2月17日 | 瞻空の勧めで「地蔵講式」を著す。 | |
| 4月14日 | 笠置寺で千日舎利講を始める。 |
|
| 秋 | 「欣求霊山講式」を著す。 |
|
| 43 建久8年 1197 | 8月 | 浄土寺(播磨国)の落慶導師をつとめる。 |
| 44 建久9年 1198 | 11月17日 | 笠置寺で十三重塔の供養をおこなう。 |
| 45 正治1年 1199 | 6月 | 後鳥羽上皇、伊賀国阿閉郡重次名を般若庄として般若台の所領とする。 |
| 後鳥羽上皇に招かれ、法相の宗旨を説く。 | ||
| 47 建仁1年 1201 | 貞慶、般若庄を春日社に寄進する。 |
|
| 5月 | 「観音講式」を著す。 |
|
| 12月 | 元興寺玉華院の信長の依頼により「弥勒講式」を著す。この頃、「勧誘同法記」を著す。 |
|
| 48 建仁2年 1202 | 8月 | 唐招提寺の東室を修理し、釈迦念仏会を始める。 |
| 浄瑠璃寺の千基塔供養の導師をつとめる。 | ||
| 49 建仁3年 1203 | 9月 | 唐招堤寺で釈迦念仏会をおこなう。 |
| 50 元久1年 1204 | 笠置寺の礼堂軒廊と弥勒堂の供養をおこなう。 | |
| 10月 | 笠置寺で龍華会を始める。 |
|
| 51 元久2年 1205 | 10月 | 「興福寺奏状」を著す。 |
| 8月 | 刑部卿三位(源範子=後鳥羽上皇の乳母)追善供養の導師をつとめる。 | |
| 12月 | 後鳥羽上皇、春日杜に御幸し、七堂を巡礼する。 |
|
| 52 元久3年 1206 | 2月19日 | 京都梅小路の南堂の供養の導師をつとめる。 |
| 4月 | 藤原定家、笠置寺で亡き九条良経の供養をおこなう。導師は貞慶。 | |
| 53 承元1年 1207 | 8月 | 「興福寺北円堂造立勧進状」を著す。 |
| 54 承元2年 1208 | 9月7日 | 河内交野の新御堂供養の導師をつとめる。 |
| 9月9日 | 9/7に後鳥羽上皇より賜わった舎利2粒を海住山に納める。 | |
| 11月27日 | 瞻空、海住山寺の扁額を書く。 | |
| 55 承元3年 1209 | 「観音講式(値遇観音講式)」を著す。 |
|
| 56 承元4年 1210 | 9月19日 | 笠置寺で『瑜伽論』供養の導師をつとめる。後島羽上皇御幸。 |
| 9月20日 | 後鳥羽上皇、瓶原にあった雅縁の「山庄堂」供養に御幸。導師は貞慶。 | |
| 9月11日 〜 翌1月15日 | 覚真(藤原長房)出家し海住山寺に入る |
|
| 57 建暦1年 1211 | 9月1日 | 九条道家と談ずる。道家「深く帰すべき人」と記す。 |
| 唐招提寺の御影堂で『梵網経古迹記』を講ずる。 | ||
| 58 建暦2年 1212 | 「真理鈔」「因明明要抄」「明本鈔」を著す。 |
|
| 59 建暦3年 1213 | 1月11日 | 「海住山寺起請五箇条」(海住山寺の規式)を代筆させ、署名する。 |
| 2月3日 | 入滅。 | |
| 建保2年 1214 | 海住山寺五重塔完成。 |
|
| 貞応1年 1222 | 慈心上人(覚真)大井手用水を完成。 | |
| 元仁2年 1225 | 2月3日 | 海住山寺で貞慶の十三回忌追善法会が営まれる。 1) 一間四面の堂舎を建立し、三尺の釈迦如来を安置し、戒律祖師像六体を図絵 2) 七間の食堂を建立し、賓頭廬尊者像を安置 3) 三間の経蔵を建立し、一 4) 本堂に「観音浄刹之藻」と「霊叡往生之画図」を安置 5) 萱葺の大門を建立 6) 塔の階の増加 |