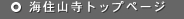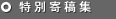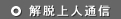海住山寺トップページへ
官僚から転身した覚真|安田次郎(お茶の水女子大学)
 海住山寺境内の南方に、貞慶上人のものとならんで慈心上人の墓所がある。慈心上人は、民部卿入道とよばれた慈心坊覚真のことで、貞慶の跡をひきついで海住山寺の復興につとめた中興二世である。
海住山寺境内の南方に、貞慶上人のものとならんで慈心上人の墓所がある。慈心上人は、民部卿入道とよばれた慈心坊覚真のことで、貞慶の跡をひきついで海住山寺の復興につとめた中興二世である。二代目といえば、目立たないひとが多い。たとえば、室町幕府二代将軍の義詮や徳川幕府二代将軍の秀忠などがよく引き合いに出される。いずれも偉大な初代の陰に隠れてしまって損をしているが、覚真はたいへん有能な人物で、経歴は少し違うが、師の貞慶に劣らない足跡を歴史上に残している。
覚真は俗名を藤原長房といい、朝廷で参議まで勤めたひとである。参議は、現在の政治家のランクでいえば、大臣や長官に相当する官職であるが、長房の家系は、政治家というよりもむしろ代々実務官僚として活躍し、長房自身も有能な役人であった。太政官で行政執行の中心となる弁官を長年勤めるとともに、摂関家のひとつである九条家の事務をつかさどる家司、後白河院に仕える院司としても能力を発揮し、後鳥羽院政発足後にはその院司として活躍している。承元2年(1208)9月7日、貞慶は河内国交野(現在の大阪府交野市)の「新御堂」供養の折に後鳥羽院から仏舎利2粒を賜ったが、これを上人のもとに届けた使者が長房であった。
後鳥羽院は文武両道の異色の帝王で、とくに和歌の道に秀でていた。長房は、『新古今和歌集』や『小倉百人一首』の撰者として有名な藤原定家などともに、後鳥羽院歌壇の形成に大きな役割をはたした。定家も九条家の家司を勤めたので、長房とはいわば同僚の間柄であり、定家の日記である『明月記』に長房はときどき登場する。
さて、承元4年9月22日、長房は海住山で出家する。ときに41歳。貞慶から受戒した。出家の理由として、ある書に「後鳥羽院、天下の事を思しめし立てられける時、長房卿は諫めかね奉りて遂に出家」したとあり、後鳥羽院が「天下の事」、つまり鎌倉幕府倒幕を企てたとき、院を思いとどまらせることができなかったからという。後鳥羽院の倒幕計画は承久の乱(1221)として失敗に終わり、院は隠岐に流されるが、それは長房が出家してから10年も後のことである。したがって、時期を重視すると、出家の理由は長房が蔵人頭として仕えた土御門天皇が後鳥羽によって承元4年に退位させられたことにあると考えたほうがいいという意見も出されている。
もちろん、以上のような政治的な契機ではなく、長房自身の「道心」を重視することもできる。長房は、華厳宗の中興の祖である明恵上人にも熱心に教えを請うており、「形は俗塵に雑(まじ)わるも、心は真際(しんさい)に住す」といわれるほどの求道者でもあったので、もともと出家遁世の志が強かった可能性もすてきれない。
理由は決めがたいが、出家後の長房すなわち覚真の活動は、大きく海住山寺の内と外とに分けられる。寺内の活動は海住山寺の二世としてのものが中心で、寺外のものとしては興福寺や春日社の修理造営が重要なものである。
貞慶の入滅によって海住山寺を引き継いだ覚真は、仏舎利を五重塔に安置し、貞慶の遺志にしたがって四季四度の談義を継承し、毎月三度の講問を始めるなど、戒律を学び修学する場としての海住山寺の整備につとめた。また、寺内に向けて何度か置文(おきぶみ)の形で僧たちの守るべきルールを定めている。それらのなかには女性の寺内居住や飲酒などに関するおもしろいものもある。飲酒に関するものを紹介すると、3人以上で酒宴を開いてはならない、ただし、同居の3人以上が「薬酒」を飲むのは仕方がない、客人であってもたやすく酒を勧めてならない、「上戸」であっても「二杯」を過ぎてはならない、などである。戒律を重んじた覚真は、完全な禁酒を理想としていたようであるが、さすがにそこまで厳しくするのは無理だと思ったのだろう。
つぎに、覚真と興福寺・春日社の修造事業の関わりに目を転じよう。
奈良の興福寺は、平氏の焼討によって平安末期にほぼ全焼した。鎌倉時代の前半は、興福寺にとっては復興の過程であった。師の貞慶が、五重塔や北円堂などの再建に勧進上人としてかかわり、重要な役割をはたしたことは既述したとおりであるが、ここでも覚真は師のあとを継いでいる。1230年代のはじめころから、覚真は大和国(現在の奈良県)を対象として勧進事業を展開した。それによって春日若宮社や興福寺の諸堂、僧坊などの修理修造が進められた。
勧進はしかし、やがて行き詰まる。覚真没後、13世紀も半ばになると、大和国には多くの勧進聖(寄付を集めて回る僧)が行き来するようになり、偽物も横行するようになった。怪しげな勧進聖が増えると、人びとは警戒して勧進に応じなくなった。
自発的な寄付が期待できなくなると、興福寺は武力をちらつかせて、また時には実際に行使して強制的に集めるようになった。こうして以後、興福寺は修造費を大和国に「一国平均」の「土打役(つちうちやく)」として賦課するようになった。「一国平均」とは一国全体に、一律に、ということで、東大寺や多武峯などの所領にもかけられた。「土打」とは瓦にする粘土を叩いて空気を抜く仕事のことで、瓦を造るときの、予備的ではあるが重要な作業である。寺院の屋根には大量の瓦が必要だったので、造営事業を象徴する労働である。土打役は、のちに米や銭の形の恒常的な賦課に転化し、中世末まで興福寺を経常的に支える重要な収入となっていく。その基礎を覚真が作ったのである。
話を覚真にもどそう。覚真は大和国を対象として勧進を行ったと述べたが、それは彼自身が労働の提供を求めてせっせと大和国内を歩いた、あるいは奈良の街頭に立って募金した、ということではない。実際に勧進に従事したのは、興福寺や末寺の僧たちである。覚真は貞慶の命によって興福寺内に常喜院を建立していたが、ここが勧進の拠点となった可能性も考えられよう。覚真は南山城の海住山寺に身を置きながら、南都の僧たちを指導、指揮したのである。
覚真が南都の僧の動向に強い影響力をもった存在であったことは、朝廷への強訴や他の寺社との紛争に際してもうかがうことができる。建保元年(1213)11月の強訴のときには覚真は後鳥羽院の側に祗候し、めまぐるしく変わる状況に応じつつ興福寺の僧たちに自重するように説得を続けた。このときは僧たちを静める役割をはたしたのであるが、20余年後の嘉禎元年(1235)の石清水八幡宮との抗争では、僧たちを宥めると言いながらむしろ扇動したと非難されている。静めるにしろ煽るにしろ、それは南都の僧たちから信頼され指導的な立場にあったからこそ可能なことであっただろう。
かつて有能な官僚として朝廷や院や摂関家で活躍した覚真は、海住山寺の中興二世とし寺院経営を引き継いだだけでなく、本寺である興福寺に対しても大きな影響力を持ち、貢献したのであった。この点でも、貞慶の忠実な継承者であったといえよう。
関連情報
- - 関連情報上横手雅敬「貞慶をめぐる人々」『日本の宗教と文化』同朋舎出版、1989年
- 黒田彰子「覚真覚書」『愛知文教大学論叢』1、1998年
- 安田次郎『中世の興福寺と大和』山川出版社、2001年