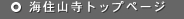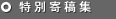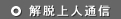���W�R���e���c�ꗗ
���W�R���e���c�ꗗ
�C�Z�R���g�b�v�y�[�W��
- ��E��l���W
- ��E��l��e�W�ꗗ
- ��E��l��e�W No.4
�C�Z�R�����̉@�{���\��ʊω������i�d�v�������j�ɂ���
 �@�C�Z�R���ɂ́A�����Ȃ���ω��̈Ќ��ƗD�낳�����˔����Ă���\��ʊω������`����Ă���B���̊ω����́A�d�v�������Ɏw�肳��A����͓ޗǍ��������ق̊���ƂȂ��Ă���B
�@�C�Z�R���ɂ́A�����Ȃ���ω��̈Ќ��ƗD�낳�����˔����Ă���\��ʊω������`����Ă���B���̊ω����́A�d�v�������Ɏw�肳��A����͓ޗǍ��������ق̊���ƂȂ��Ă���B�`�� �{���̓`���ɂ��ẮA�w�R�B���Վu�x�i�������N�@1711�j��w�s�����}�G�x�i���i��N�@1780�j�ɁA�����̚��@�̖{���Łu�\��ʊω�������ڎ������@���E��l�v�Ƃ���A�w�r���Í��u�x�i���ۂQ�N�@1742�j�ɂ́A�J�R���Ɂu�{���\��ʊω��A�䒷���ڗ]�A�����J�R��c��l�̎�蕧��v�Ƃ���B��c�̍�Ƃ����̂́A�{���̐���N�オ�㐢�I�ɑk�邱�Ƃ�����ł��邪�A��蕧�A�܂�O�����Ƃ����`���͐M�ߐ��������� �v����B����́A��c�̊ω��M�ƁA�{���̑傫�����l���Ă̌̂ł���B
���̊T�v�Ɠ��� �@���S�̂̓����́A�o�����X���悭�L�т₩�ȑ̋�������A���g�͒��肪�����āA�߂͂��̎������悭�\�킳��Ă���B�\��ʊω��̏ے��ł��铪��ʂ́A����ɕ��ʁA韂̒��قǂɎO�ʁi���ʂ͕�F�ʁA�����ѓ{�ʁA�E�͉��o�ʁj�A�n���̏�Ɏ��ʂ�z����B�E����{���؈�Ƃ��A����͕I���Ȃ��Đ��r������A��q����悤�ɑ̋�ɓ�����\���Ę@����ɗ��B ����ʂ̓����́A�e�ʂ����₷���A��������Ƃ����\���ƂȂ��Ă��邱�ƁB�����Č��̑�Ζʂ��A�ڂɂ͓{����݂��Ȃ���A����傫���J���ď��Ă��邱�Ƃł���B���̖ʂ́A�V�����ɂ͖ڂ��ׂ߂đf���ɏ����A�@�؎��\��ʊω����Ŗ{���Ɠ��l�̕\����������悤�ɂȂ�B���̕ω��́A�\��ʊω��o�T�̂����A��ɛ�����∢�n�ؑ���Ȃǂ̌Â����̂́u��Ζʁv�Ƃ���A������ł́u�\����Ζʁv�ƕ\�L����邱�ƂɑΉ����Ă���ƍl������B�܂�{���̌��ʂ́A�\���̑��ł�������Ă���Ƃ����s�v�c�Ȋ��\�����Ă���̂ł���B
�@������45,6�p�B����ɋ߂��傫���̏\��ʊω��������������o����B�������������ّ�42,1�p�A�R���E�_������44,7�p�i���㕧�ʌ��j�A�ޗǍ��������ّ�42,8�p�A���E���~����45,0�p�A�O�d�E���R����47,6�p�A���m�E�|�ю���48,8�p�Ȃǂł���B���̂悤�ɋ߂������̍�Ⴊ�������o���闝�R�Ƃ��ẮA�\��ʊω��o�T�ɁA���͔��h�Łu��P�c�蔼�v�̑傫���ɑ���Ɛ������ƂƊW������̂ł��낤�B�����́A���h���ƌĂ�Ă���B
�@�ł́A�{���̗p�ނ͂Ƃ����ƁA��������Ƃ����ʊ��̂���d���̍ނŁA�J���Ƃ������������邪�A���̎������炷��A�o�T�ʂ蔒�h�̉\�����ے�ł��Ȃ��B
�@�\���́A����瓪�����@���Ɏ���܂Œ��o����B�ڂ�������ƁA����ʂ�韂̎O�ʂ͋����獏�݁A���̎��ʂ͕ʍސ��ŐA���t������B�E��͎w��܂ł��ׂāA����͕I�܂ł����ƂȂ�B���݂́A�@�����𐳕��`�ɐ؎��A���̘@���ɂ͂ߍ���ł���B
�@��╔�́A���o�ʂ̈�ʁA���ʉ����A����̑O�M�������A�E���Q�E�R�E�S�w�̈ꕔ�A�V�߂̗��r�O���ł���B�܂��A���w�E��������B�����āA������̐悪�����Ă���B
�@�ʐF�Ƃ��ẮA��雂ɗΐ��c��A���͖n�ł��̗�������Ŋ���A�O�͎�ł��邱�Ƃ��킩��B���̑��A�ؔ��̑S�ʂɈÎ�n�̐F���F�߂���B���邢�͑h�F�Ő��߂Ă���̂�������Ȃ��B
�@���݁A�������A�����O�A�������A�`�ɏ����A���������ɓ��B���c��A�ʍސ��̑��������������Ղ��c���Ă���B�\��ʊω��o�T�̖�ɛ�����∢�n�ؑ���ł́A���h����u���̑��g�ɐ{�炭��������o����������v�Ƃ���A�_���������͂��߂Ƃ��Ĉ���瑕���i��o����Ⴊ����B�������A������ɂȂ�Ɓu���̊ώ��ݕ�F�̐g��ɁA���ⓙ�̎�X�̑��������v�Ƃ���A�O�҂̑����������獏�o����Ƃ����j���A���X�����ނ��A���������������Ă���悢���Ƃ��q�ׂĂ���B���̂悤�ȕω���{���́A���f���Ă���̂ł��낤�B
�@�����������獏�o���邱�Ƃ́A�g�̕\���ɐ�����݂��邱�Ƃɂ��Ȃ邪�A��؍��o����̉���́A�g�̐����\���ɕ\�����邱�Ƃ��\�ɂ����̂ł͂Ȃ��낤���B
�����̖ړI�Ƃ��̈Ӗ� �@�ȉ��ɖ{���̐g�̐��ɒ��ڂ��Ă݂悤�B�܂����ʂł́A�������ɔP��A�E�G�������Ȃ��Ă���B���̓�̓����͘A��������̂ŁA�E�����グ�悤�Ƃ��Ă��邱�Ƃ��`����Ă���B���ʂɂ����ẮA�㔼�g�炵�Ă��邱�ƁA�����͂��̏�ɐ^�����ɗ��Ă邱�ƁA�E��͕I������O�ɏo���Ă���B���ʂ̓����Ɗ֘A���Ē��߂Ă݂�Ƃ��A�ω����͍��𒆐S�ɁA�E��ƉE����O�ɏo����������Ă���B
�@���̂悤�Ɍ��Ă���ƁA�{���̑��`�I�ȖڕW�́A��̒��ł����ɓ�����\�����邩�Ƃ����e�[�}�ɂ������Ǝv����B�{���͂��̃e�[�}���A���Ɍ����ɂ��Ȃ��Ă���̂ł���B
�@���̂悤�ȑ̋�̓�����\���\��ʊω����́A�V�����ɂ͌���ꂸ�A�@�؎��A�n�ݎ��A�H�����̏\��ʊω����Ƃ��������������̖��i�ɂ݂���悤�ɂȂ�B�O�d�����R���̏\��ʊω����ł́A�����̓����ɉ����āA�E���������グ��Ƃ�������Ղ��\�����̗p���Ă���B
�@�{���́A�����̏\��ʊω����Ɠ��������鑢���v�z�̂��Ƃō��ꂽ�ƍl�����邪�A���̒��ɂ�����\����̓����Ƃ��āA���ʂ̏�����Ɉ��グ�A���ɂ�������Ƒ�����݂��邱�Ƃ��w�E�ł���B�܂����̌���́A�����l�ɔw�ʂɈ������B���̏�����̕\���́A�@�؎���n�ݎ����ɂ݂�����̂ł���B�������A�@�؎����Ȃǂł́A������݂��Ȃ��B�����I���̖@������ʊω����͑�����݂��邪�A���S�̂������グ�āA����͘@����ɂ��Ȃ��B����Ė{���́A������̖@�؎����Ȃǂɂ݂�����������\���ƂƂ��ɁA�V�����ɑ��݂��Ă����@���������̌Ñ��Ɋw��ŁA�V�����\�������グ�Ă���ƌ�����̂ł͂Ȃ��낤���B���݂ɁA���̍�����ɂ݂��錋�іڂ��A�V�����̊������ɕ\����Ă�����̂ł���B
�@�ł͈�́A�\��ʊω����̑̋�̓����͉����Ӗ�����̂ł��낤���B���̈Ӗ������߂ď\��ʊω��o�T�ɋ��߂Ă݂悤�B
�@������A���̂��ƂɊW����Ǝv���镔����v��A���h����p���āA���萬�A�̂��߂̏C�@���s���A���ꂪ��������Ƃ��A��n�͗h��A���͓����A�ŏ�ʂ̌���萺����������Ɛ����Ă���B��ɛ�������ш��n�ؑ���ł́A�u�ϐ�����F�A����ɗ������A���̐�h���͎��R�ɗh�����v�Əq�ׂĂ���B
�@�F�肪�ω��ɓ͂����Ƃ��Ă̊���q�ׂ��Ă���̂ł���A�̂ɑ����̍ŏI�ړI�����̊�̊l���ɂ������Ƃ�������B�����ł́A���̊�̂����ɁA�����������Ƃ����߂��Ă����_�����ڂ���悤�B
�@�����������Ƃ̔w�i���A������ł͂͂�����Ƃ͐����Ȃ����A��ɛ�������ш��n�ؑ���ɂ��A�ω���F�̓���ւ̗��ՂƂ����l������������Ă���B�܂�����Ɋւ��āA������𒍎߂����d���́w�\��ʐ_���S�o�`�`�x�ł́A�u�ϐ����͕K�����h�Ɉ˂�Đ��������킷�v�Əq�ׂĂ���B���̂悤�Ȃ��Ƃ���A�䍑�̐_������Ɉ˂�悤�ɁA���h���Ɋω����̂��̂��˂邱�Ƃɂ��A���������ƍl�����Ă��邱�Ƃ���������悤�B���̂��Ƃ͌���������A���h�ɂ��ؑ����A���g�̊ω��ւƕω��𐋂����Ɖ�����邱�ƂɂȂ낤�B
�@�ȏ�̂悤�ɁA�\��ʊω����ɂ����铮���̕\���́A�F��̌��ʂƂ��Č�����̌`�ł���A�ω��̗��Ղɂ�鐶�g���ւ̓]�����]�܂ꂽ�p�ł���ƌ����悤�B
�@�Ō�ɁA�{���̂�⌵�����\������o���v�f�ł���A�ׂ������ڂɂ��ĐG��Ă��������B
�@���̖ڂ̕\���́A���ʂ�����ґz���邩�̂悤�ɔ��Ε����Ă���B�������A�����������u���A��������q���鎞�A���̖ڂ��͂�����ƌ��J���A���C���h���̂ł���B���̎��A�g�̂̓����Ƌ��ɁA�ω��̏o��������Ƀ��A���e�B�[�𑝂����̂Ǝv����B
�֘A���
- - �Q�l�������ꖫ�u�\��ʊω����̕\���|���{�ɂ�����W�J�𒆐S�Ƃ��ā|�v
�i�w�V���N���[�h�w����11�@�ω���F���̐����ƓW�J�x2001�@�V���N���[�h�w�����Z���^�[�j