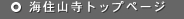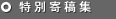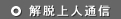海住山寺トップページへ
絵巻の貞慶、戒律の貞慶|五味文彦
貞慶の籠居 貞慶は藤原通憲(信西)の孫で、信西の右腕となって朝廷の実務官の弁官を勤めた貞憲の子である。平治の乱(1159)で祖父が殺され、それに父が連座したことにより、興福寺に入って伯父の覚憲に学んだ。寿永元年(1182)に興福寺の最も重要な法会である維摩会の竪義を勤め、文治二年(1186)にはその講師を勤めている。
貞慶は藤原通憲(信西)の孫で、信西の右腕となって朝廷の実務官の弁官を勤めた貞憲の子である。平治の乱(1159)で祖父が殺され、それに父が連座したことにより、興福寺に入って伯父の覚憲に学んだ。寿永元年(1182)に興福寺の最も重要な法会である維摩会の竪義を勤め、文治二年(1186)にはその講師を勤めている。建久二年(1191)から摂関の九条兼実との接触が深まり、その日記『玉葉』にはしばしば登場している。それを見ると、同年二月二十一日の法華八講の結座の講師を勤めた貞慶について、兼実は「説法珍重」「談と云ひ、弁説と云ひ、末代の智徳也。感ずべし」と賞賛しており、南都に下って興福寺の南円堂で聞いた貞慶の表白も「甚だ優」であったといい、さらに十月十一日の般若心経と金剛般若経供養の講師での「演説」については、「感涙、実に神明三宝と雖も争かこの理に伏せしめ給はざらんや。殆ど神と謂ひつべきか。尊ぶべし尊ぶべし。この感応必らず空しからざるべき者也。」とまで褒めちぎっている。
こうして貞慶は興福寺の学僧として説法の上手としても知られていったが、翌年の建久三年二月に、兼実は貞慶に籠居の意思があるとの噂を聞いた。そこで真意を尋ねたところ、籠居は「冥」により思い立ったものである、と知り、その意趣が貴いものと評価するとともに、幾つかのことを尋ね、貞慶が「大明神を祈請する」と語ったのを書きとめている。
「冥」とあるのは、二年前の建久元年十一月に貞慶が記した笠置の弥勒龍華会での願文などから考えると、弥勒菩薩を始めとする冥の仏たちのことであり、「大明神」とはもちろん春日大明神のことであって、それらの告知や神託により籠居の意思を固めたものとわかる。建久六年十一月十九日に貞慶が記した笠置般若台の供養願文は、「春日大神に申し、我が仏道の加護を頼み、大般若経の写経を終える頃、百日の社壇参詣を行った」と記しており、貞慶が遁世するにあたっては、春日大明神が大きな意味をもっていたことがよくうかがえる。
その遁世の時期について、大般若経の写経の翌年のことと見え、『弥勒如来感応抄』が引く大般若経理趣分の奥書には、写経は建久三年十一月に終えたとあるので、貞慶が兼実亭を訪ねたのは、その写経の最中の建久三年二月であって、その頃から遁世を考えていたことがわかる。「翌年の秋の蟄居」とあるのは、同書に「去去年の秋、当山に移住し、以て終焉の地となす」と見えることから、建久四年の秋の笠置への移住を意味していよう。これ以後、般若台や十三重塔を建立して笠置寺を整備する一方、龍香会を創始して『弥勒講式』を作るなど弥勒信仰をいっそう深めていった。
こう見てくると、絵巻の話はこの笠置籠居までの貞慶の動きを描いたものとわかる。しかし貞慶はこのまま笠置に籠居して終わったのではなく、世俗に再び足を染めるようになった。それは建久九年(1198)頃からである。
後鳥羽上皇と法然 貞慶は建久九年(1198)十一月の興福寺から鎌倉幕府に訴えた牒状に執筆の労をとっている。和泉の国司の使者が、春日の神人を後鳥羽上皇の熊野御幸の経費を拒んだとして捕えて、簾に巻いたうえ、賢木を焼いたという事件に関するものである。興福寺が朝廷に訴え、国司は流罪になったのだが、知行国主の平親宗には何も罪が及ばなかったことから、これはおかしい、と訴えたものである。
神威永く廃れば、仏法争か住持せん。仏法若し衰へば、王法又如何。
君一人の少臣を惜しみ、寛仁恵沢の慈しみたりと雖も、
神三宝の大瑕を惜しみ、定めし和光同塵の誡めを加へん者か。
この事件は、翌正治元年(1199)七月に平親宗が亡くなって終わるが、その親宗が春日の神罰によって地獄に堕ちた話が『春日権現験記絵』巻六の二段に描かれている。そこに貞慶の名は見えないものの、貞慶の絡んだ話として絵巻には載せられたのであろう。
貞慶が後鳥羽上皇に仕えるようになったのはこの頃からで、正治元年六月に上皇は笠置の般若台での霊山会の用途として伊賀国の荘園を寄進しており、その翌年には貞慶を水無瀬殿御所に招いて、法相の宗旨を尋ね、貞慶から「報恩講式」を送られている。元久二年(一二〇五)には上皇の乳母であった藤原範子の追善の仏事にも導師に招いている。 このように積極的に貞慶が上皇との関係を持つようになったのは、法然が建久九年に『選択本願念仏集』を著しその信仰が広がり始めていたこととも深い関係があったろう。貞慶が兼実に笠置への籠居を告げていた頃から、法然はしばしば授戒のために兼実亭を訪れていたが、この著作を契機に広く念仏の専修を訴えるようになり、兼実もその影響を受けるに至った。これにまず危機感を覚えたのが兼実の弟で天台座主になった慈円である。「九条殿ハ、念仏ノ事ヲ法然上人ススメ申シヲバ信ジテ、ソレヲ戒師ニテ出家ナドセラレ」と、兄の法然に対する傾倒ぶりを見て、天台教学の興隆を思い立ち、元久二年には大懺法院という仏教興隆の道場を建てている。
貞慶も法然らの動きに危機感があって、元久二年(1205)に法然の専修念仏を批判し停止を求めた興福寺奏状の起草にあたっている。その前年に比叡山の僧徒が専修念仏の停止を迫って奏状を出すと、法然は『七箇条制誡』を草し、門弟百九十名の署名を添えて出し自戒したのだが、弟子たちには一向に反省する意思がなく、「上人の詞には皆表裏有り、中心を知らず、外聞に拘る勿れ」とさえいう始末であったという。
そのことから、法然の考えについて九つの失を指摘し、その宗旨を論破しようとしたのが興福寺の奏状であり、この訴えによって念仏停止の宣旨が下され、建永二年(承元元年・1207年)には法然は土佐国(実際には讃岐国)に流されている。
海住山寺の貞慶 貞慶が後鳥羽上皇とのかかわりで媒介をしたのは、院に仕えた興福寺別当の雅縁と院近臣の藤原長房の二人と見られている。
このうち雅縁は上皇の後見であった源通親の兄で、建久九年から興福寺別当になり、正治二年には上皇を興福寺・春日社に迎えたが、その時の御所は雅縁の松林院であった。元久二年十二月にも上皇を南都に迎えたが、この時は雅縁の二条房が御所とされ、そこでの一切経の供養の導師は貞慶であった。
承元四年九月に上皇は笠置に赴き、貞慶を導師にした『瑜伽論』の供養に臨み、続いて南山城の瓶原にある雅縁の山荘堂供養に臨幸したが、その導師も貞慶である。雅縁と貞慶を結んでいたのは弥勒信仰で、雅縁は発願して大和の大野寺に弥勒の石仏を造っている。
他方、長房は建久二年(1191)に後鳥羽天皇に蔵人として仕え、建久五年からは弁官を勤め、建仁二年(1202)には蔵人頭となっている。貞慶の父と同様に有能な官僚であったことからも、貞慶と上皇を媒介したのであろう。長房は高尾の明恵との親交もあって、高山寺の興隆に大きく寄与しており、同じく道心のある官僚として貞慶に接したものと考えられる。貞慶が興福寺や春日社のことについて朝廷に訴えた際には大いに援助したものと見られ、なかでも貞慶が法然の念仏宗の失を訴えたときには、その訴えをよく伝えたことであろう。
そうしたなかで長房が貞慶を援助して再興したのが海住山寺である。承元二年(1208)、貞慶は上皇の発願により造られた河内の交野御堂の供養の導師を勤め、このときに上皇から仏舎利二粒を与えられたが、その舎利の使者は長房であり、舎利は貞慶によって海住山に安置された。しかもその二年後に長房は道心から貞慶のもとで出家し、覚真と号したばかりか、建保五年(1217)の貞慶の死後には海住山寺の二世となっている。
貞慶が海住山寺に求めたのは戒律である。貞永元年(1232)に覚真が定めた雑事三箇の第一条の「当山修学の事」では「此処戒律を学ぶべきの由、先師慇勲の教命也。」と記していて、 戒律を学ぶのが「先師」(貞慶)の教えであったといい、次の第二条でも「往山僧侶の衣服等威儀の事」と衣服の威儀を正すことを規定している。また貞慶が生存中に定めた起請五箇条の第一条には「不可令当山内輙許住尼衆等事」と、僧尼が雑居するのを許さないと規定されている。
貞慶は法然の念仏宗を批判するなかで戒律の重要さを痛感したのであり、海住山寺はその道場として長房の援助によって再興されたものと考えられる。貞慶の学問の中心をなしたのが法相・弥勒信仰・律の三つであったことはよく知られているが、そのうちの法相を担ったのが興福寺であり、弥勒信仰を担ったのが笠置寺、そして律を担ったのが海住山寺であるという関係になろう。貞慶は順次、これらに住むことになって、最後に海住山寺に住んでその死を迎えたのである。
絵巻には海住山寺の貞慶を描いていないが、それは戒律を強調していた時期の貞慶だったからであろう。貞慶が重視した戒律は、絵巻が描かれた鎌倉時代の後期には叡尊や忍性らによる西大寺律宗として違った発展をなしていたので、それを絵巻に描くことはなかったのである。
12
関連情報
- - 関連リンクNo.26|絵巻の貞慶、戒律の貞慶 その1
- - 参考文献五味文彦「『春日験記絵』と中世」淡交社、1998年
- 田中稔「海住山寺の歴史」
(『大和古寺大観 巻七 海住山寺・岩船寺・浄瑠璃寺』岩波書店、1978年)
- 上横手雅敬「貞慶をめぐる人々」(『権力と仏教の中世史』法蔵館、2009年