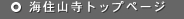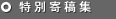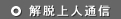海住山寺トップページへ
海住山寺二世慈心房覚真の在俗時代 その一
 海住山寺二世慈心房覚真(俗名藤原長房)は、承元四(1210)年九月二十二日、解脱房貞慶の戒を受けて出家した。その後仁治四(1243)年正月十六日、七十六歳で薨ずるまでの後半生を、荒廃した海住山寺の復興に尽力した。五重塔は貞慶の意志を継いで覚真が完成させたものである。覚真は貞慶の高弟であるとともに、神護寺の明恵とも親しく、また、興福寺との関係を示す資料も残っている。
出家後の覚真については、宗教学の立場から多くの研究がなされており(注1)、覚真に関わる文書類も整理されているから(注2)、それらの論考や資料を参照頂きたい。
海住山寺二世慈心房覚真(俗名藤原長房)は、承元四(1210)年九月二十二日、解脱房貞慶の戒を受けて出家した。その後仁治四(1243)年正月十六日、七十六歳で薨ずるまでの後半生を、荒廃した海住山寺の復興に尽力した。五重塔は貞慶の意志を継いで覚真が完成させたものである。覚真は貞慶の高弟であるとともに、神護寺の明恵とも親しく、また、興福寺との関係を示す資料も残っている。
出家後の覚真については、宗教学の立場から多くの研究がなされており(注1)、覚真に関わる文書類も整理されているから(注2)、それらの論考や資料を参照頂きたい。在俗時代の覚真、藤原長房がいかなる人物であったのか、という問題は、私のように日本文学を研究する者にとっては、非常に興味ひかれるところである。
長房は、文学史には少なくとも二度登場する。一度は、後鳥羽院歌壇の成立に深く関わった院近臣として。もう一度は、徒然草に登場する人物として。まずは、長房の出自と官歴から語るべきであろう。
長房は、勧修寺流(為房流)藤原光長男、光長の兄は吉田経房である。経房は平安末期から鎌倉期に至る激動の時代を映した『吉記』を残すとともに、広義の関東申し継ぎの任にもあって、この時代を知る上で極めて重要な人物である。また、仁和寺隆遍も兄弟である。光長は三事兼帯(五位蔵人、弁官、検非違使佐を兼帯することで、これを許されたということは、実務能力に秀でた官僚であったことを示すとともに、極めて名誉なことでもあった。なお、光長の兄弟はでは、経房・光長、定房の三人が三事兼帯を果たしている)、後鳥羽天皇の文治元年から二年にかけて蔵人頭を務め、のち参議、勘解由長官、九条三位とよばれた官人であるとともに、九条兼実の家司でもあった。すなわち典型的な実務官僚であり、後鳥羽政権の中核に深く関わる家柄でもあったのである。長房は光長の長子、母は参議俊経女である。弟に宣房、仁和寺小僧都光遍がいる。光遍の付法の師はもちろん隆遍である。父光長は始め松殿基房の家司であったが、寿永元年 (1182)十二月より兼実の家司となっており、長房自身も文治二年に十七歳で九条家家司の列に加えられた(玉葉)。
これを要するに、長房は、勧修寺流の家に生まれ、実務官僚としての道を歩むと同時に、九条家の家司でもあったということである。長房の官歴はほぼ忠実に父光長のそれを辿っている。承元三年には、猶子定高(父光長晩年の子で、長房猶子となっていた)の右少弁昇進を願い出て、自らは参議を辞した。したがって翌承元四年の出家が、官途の停滞などによるのでないことは言うまでもない。勧修寺流という家格から見て、長房は功成り名遂げたと言うべきであろう。
右中弁であった建久九年(あるいは建久五年という説もある)、長房は仁和寺にいた上覚(明恵の叔父)という僧が著した歌学書『和歌色葉』を、後鳥羽院に献上する際の仲介をしている。この間の事情は、『和歌色葉』に付けられた書状によってわかるのだが、長房は単なる仲介をしたに止まらず、上覚に歌学書の執筆を慫慂した可能性もある。直接仲介の労を執ったのは長房の弟宣房であるが、さらにこのやり取りには仁和寺にいた弟の光遍も関わっており、後鳥羽院―長房 ―宣房―光遍―上覚というつながりが見て取れるのである。後鳥羽院と言えば、後年、新古今和歌集の成立に深く関与する稀代の歌人帝王であり、定家や家隆と共に、華やかな新古今歌壇を形成したが、建久年間にはまだ定家、家隆ともに、良経(九条兼実男)を中心とする九条家歌壇で研鑽を積んでおり、後鳥羽院との出会い以前であった。新古今歌壇は、良経達の九条家歌壇が、後鳥羽院歌壇と統合されるようなかたちでできあがったと考えられるが、その後鳥羽院歌壇について、久保田淳氏は「ずぶの素人集団で、その詠歌の場の設営に当たっていたのは儒学者を含む実務官僚だった」と言われている。長房は、その中心にいたのではないだろうか。初学期の後鳥羽院は、詠作に励むと共に、歌学をも学習していたのであろう。その際、『和歌色葉』のような、初学者にも理解しやすい網羅性を持った歌学書が必要であったと考えられる。その後、後鳥羽院歌壇は新古今歌壇へと発展的に解消し、後鳥羽院は熱狂的な詠作活動に入っていく。長房は歌人ではないけれども、たとえば後鳥羽院の熊野御幸にはしばしば同道し、王子ごとに行われた歌会で詠歌している。 正治二年六月二十八日の詠。題は「荻風増恋」。
いもがすむこれやそなたの風ならん荻吹く音のことに身にしむ
こうした活動は、やがて新古今和歌集成立へと結実していくのであり、始発期の後鳥羽院歌壇の形成に、長房が院近臣として果たした役割は、決して小さいものではなかったであろう。関連情報
- - 注釈1平岡定海氏「日本弥勒浄土思想展開史の研究」『東大寺宗性上人之研究並史料下』、黒田俊雄氏『日本中世の国家と宗教』、冨村孝文氏「貞慶の同朋と弟子達」『宗教社会史研究』、保井秀孝氏「貞慶の宗教活動」『日本史研究』、上横手雅敬氏「貞慶をめぐる人々」『日本の宗教と文化』、奥田勲氏「明恵と慈心房覚真」『小林芳規博士退官記念国語学論集』
- - 注釈2佐脇貞明氏「海住山寺文書」『史学雑誌』、奈良国立文化財研究所『海住山寺総合調査報告』
- - 注釈3久保田淳氏「後鳥羽院歌壇の形成(一)」『藤原定家とその時代』
- - 関連リンクNo.07|海住山寺二世慈心房覚真の在俗時代 その二
- No.08|海住山寺二世慈心房覚真の在俗時代 その三