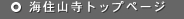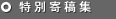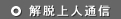海住山寺トップページへ
解脱上人寄稿集一覧
唯だ願はくは永く観音の侍者となり、生生に大悲法門を修習せん。
衆生の苦を度すこと大師に異ならず。
我もまた当来には観自在沙門と名のらん。
 上の文章は、解脱上人貞慶(1155-1213 )の言葉として知られているものの一つです。これを見ると、上人は観音の大悲の願に深く共感され、永く観音の侍者となって自らも衆生を済度する大悲行を実践し、将来、自分も観自在沙門(観音・観世音)と名のりたいという熱い願いを持っておられたことが知られます。
上の文章は、解脱上人貞慶(1155-1213 )の言葉として知られているものの一つです。これを見ると、上人は観音の大悲の願に深く共感され、永く観音の侍者となって自らも衆生を済度する大悲行を実践し、将来、自分も観自在沙門(観音・観世音)と名のりたいという熱い願いを持っておられたことが知られます。周知のように、解脱上人は法相宗の著名な学侶でした。この宗では「唯識−唯だ識のみ−」と説いて、愚かな識(こころ)を起こしては迷いのすがたを浮かべ、種々の煩悩を引き起こしては苦悩する私たちのあり方をまず明示し、次いで愚かな心(愚癡)を転じて明らかなる智慧(菩提)を成就して仏陀となる道を説いております。悟りを成就して円かなる智慧が輝くようになれば、すべての「いのち」が尊い光を放って存在(仮有)している姿がありのままに見えるようになります。この尊い「いのち」に対して如来の大慈悲が発動するのです。このような如来のあり方を自己の理想的な到達点と考えて智慧と慈悲の二行を怠ることなく錬磨している存在が、他ならぬ菩薩です。そこで、大乗仏教ではたくさんの仏・菩薩の存在が説かれ、菩薩行の実践が広く勧められたのです。実はここに、上人の観音信仰が展開する素地もあったのです。
今も昔も、観音は大悲深重の尊者として、世に広く知られております。その「いわれ」は、すでに観音という名前にも込められております。
すなわち、観音とは苦悩の中に喘ぐ人々が「南無観音菩薩」と称える音声を智慧の眼で観じとって済度する尊者の意なのです。そこで、『法華経』の「観世音菩薩普門品」(『観音経』)では、観音が三十三の姿に身を変えて人々を救うあり方も示されるようになり、やがて観音は現世利益を代表する尊者として広く信仰されるようになりました。しかし、上人の観音信仰は、このような世間一般の信仰とはかなり異なるものでした。決して自らの救済を求めるのではなく、あくまでも衆生を救済する菩薩行の実践を志して観音へ帰依していかれたのです。海住山寺ご移住の翌年である承元三年(1209)に著された『観音講式』には、『華厳経』に示される「我と共に菩薩道を実践せん」という観音の悲願に深く共感して観音に帰依なさったあり方が明確に示されているのです。
では、いつ頃、上人は観音に帰依なさったのでしょうか。近年になって発見した東大寺蔵の『観世音菩薩感応抄』には、上人がすでに観音に深く帰依しておられたあり方が示されております。本書には「般若臺」という言葉がしばしば出てまいりますので、笠置に蟄居なさった建久五年(1194)以降の著述であったことは明らかです。したがって、上人の観音信仰は笠置時代にはすでに確立していたと考えられるのですが、それが具体的な形として現れてくるのは承元二年(1208)の海住山寺ご移住だったといってよいでしょう。
海住山寺 ―――。何と魅惑的な名前でしょうか。実は、この寺号は上人ご自身がおつけになったもので、『明本抄日記』という書物には「観音の誓願海に安住するという意味で名づけた」という旨が記されております。まさしく「観音と共に大悲の行を実践したい」という上人の熱い思いが結実した命名であったといってよいでしょう。この地で観音親近の行を実践なさること約四年、建暦三年(1213)二月に上人は示寂なさるのですが、その前年の末に弟子が口述筆記したという『観心為清浄円明事』という書物には、「病席での雑談は多く観音補陀落のことばかりであった」とありますので、臨終を迎える頃の上人の願いは、まさしく観音の補陀落浄土へ往生したいという点にあったといってよいでしょう。
年が明けて上人はやや回復なさいますが、二月になると急に様態が悪化し、三日になって「臨終の式」を行ない、入滅なさいました。このときの「臨終の式」なるものについて、『解脱上人御形状記』や『山城名勝誌』などには、「西南の方角にある観音の補陀落浄土に向かって端座し、観音の宝号を唱えつつ入滅した」と記されております。実に見事なご最期であったといってよいでしょう。とはいえ、人が死に往くときは苦しいものです。なぜ上人は臨終の時に病をおして、このような「臨終の式」をなさったのでしょうか。これについては次回、お話することにいたしましょう。
関連情報
- - 関連リンクNo.18|解脱上人小話 第二話『解脱上人 臨終の式を厳修なさる』
- No.19|解脱上人小話 第三話『解脱上人 浄土を願生なさる』
- No.21|解脱上人小話 第四話『解脱上人 地獄を語りなさる』