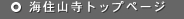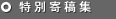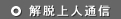海住山寺トップページへ
解脱上人小話 第四話『解脱上人 地獄を語りなさる』|楠 淳證(龍谷大学教授)
我もし暫時に冥途に往きて閻魔王に就いて心の所願を乞わんに、王の加被に よって一の地獄に到らん。先亡の恩愛、もしは其の中に堕して其の苦を受け ん。三熱の地の洞燃の焔の中に宛転として呼叫する声、鉄城に満つ。忽ちに 我を見おわりて悲喜して我に語る。「吾むかし愚盲にして善悪をわきまえず、 無量の悪を造る。因果は堅猛にして大劇苦を受く。吾むかし罪を造ること多 くは汝のためなり。我いま苦を受く。汝、何んぞ救わざるや」と。皮骨焦げ 尽きて其の形を見ざれども、言語髣髴として昔の声に似たることあり。告げ おわりて須臾に火聚の中に入る。時に目は昏れ魂は消え、頭を叩き脳を割き、 悲感熾然なれども助けるに力なし。我たとい此の事に遇わんに堪忍すべきや 否や。深重の大悲、此の時に盍んぞ生ぜん。
 上の文章は、解脱上人(1155−1213)がお書きになった『心要鈔』二利門の一節です。ここで上人は、「閻魔王に乞うて地獄に行ったとしたら・・・」と仮定して、地獄の苦の様相を語られ始めます。それによりますと地獄の苦悩は量り知れないほどで、ある者は焼かれ、ある者は煮られ、ある者は斫られ、ある者は截たれる。また、ある者は刺され、ある者は懸けられ、ある者は磨される。炎の中を転げ回って絶叫する声が地獄の城(鉄城)の中に満ち満ちて絶えることがないのだと、上人はご描写なさいます。そのあり方は源信和尚の『往生要集』の記述を彷彿とさせるものがありますが、ご両者の説示の目的は大きく異なっております。すなわち、源信和尚が人々に苦悩の世界(穢土)を厭い離れて安らぎの世界(浄土)を欣い求めさせようとして地獄の様相をお説きになったのとは異なり、解脱上人は地獄で苦しむ亡者の姿を示して人々に大悲心を発させようとなさったのです。そのため、上人は特に「恩愛の者」の苦悩の描写に工夫をこらされました。それが上の文章です。人というものは親子の情愛にどっぷりと浸って暮らしているものです。そのマイナス面をよくよくご承知の上で、なおかつ父母親近の縁を尊重なさったお方が解脱上人でした。そこで、なぜに大悲の行を実践するのかという問いをお立てになるに際しても、上人は最も身近な「父母の恩」を例示して、「深重の大悲をおこせ」というご教示の仕方をなさったのです。
上の文章は、解脱上人(1155−1213)がお書きになった『心要鈔』二利門の一節です。ここで上人は、「閻魔王に乞うて地獄に行ったとしたら・・・」と仮定して、地獄の苦の様相を語られ始めます。それによりますと地獄の苦悩は量り知れないほどで、ある者は焼かれ、ある者は煮られ、ある者は斫られ、ある者は截たれる。また、ある者は刺され、ある者は懸けられ、ある者は磨される。炎の中を転げ回って絶叫する声が地獄の城(鉄城)の中に満ち満ちて絶えることがないのだと、上人はご描写なさいます。そのあり方は源信和尚の『往生要集』の記述を彷彿とさせるものがありますが、ご両者の説示の目的は大きく異なっております。すなわち、源信和尚が人々に苦悩の世界(穢土)を厭い離れて安らぎの世界(浄土)を欣い求めさせようとして地獄の様相をお説きになったのとは異なり、解脱上人は地獄で苦しむ亡者の姿を示して人々に大悲心を発させようとなさったのです。そのため、上人は特に「恩愛の者」の苦悩の描写に工夫をこらされました。それが上の文章です。人というものは親子の情愛にどっぷりと浸って暮らしているものです。そのマイナス面をよくよくご承知の上で、なおかつ父母親近の縁を尊重なさったお方が解脱上人でした。そこで、なぜに大悲の行を実践するのかという問いをお立てになるに際しても、上人は最も身近な「父母の恩」を例示して、「深重の大悲をおこせ」というご教示の仕方をなさったのです。解脱上人の祖父は、平治の乱で知られる藤原信西入道です。信西入道はこの乱で実権を失い、自害いたしました。上人の父であった藤原貞憲もまた、これに連座して官を解かれ、出家したといいます。他の兄弟が解官配流になっていることを考えると、あるいは貞憲も流罪に処せられていたのかも知れません。近年、東大寺で発見した『観世音菩薩感應抄』には、「家、常州に在りし昔より・・・」と上人自らお述べになっているくだりが出てまいりますので、幼い頃のひととき、上人に常陸の国(今の茨城県)でお過ごしになられた不遇のときがあったのかも知れません。そして、八歳のときに出家。年を経て『観世音菩薩感應抄』をお書きになられた頃(1200年頃か?)になると、悲しいかな、父は「洛下の隠士として大和の国(今の奈良県)の片隅に栖まう身」、母は「下賤の生業をする身」となりはてていたのです。このことを深く悲しまれた上人は、父母の救済を願って種々に心を砕かれるのですが・・・。そう考えると『心要鈔』の上の一文もまた、このような背景を伴って記されたものであったことがわかります。地獄の猛火の中で「私がむかし罪を造って大劇苦を受けているのは全てお前のためである。なぜ救ってくれないのか」と悲嘆するかつての父母の声を聞いたとき、どうして「有情を悲しむ深重の大悲を生じないことがあろうか」と上人は慟哭され、「我が身に当てて悲哀の心を発せ」とご教示なさったのです。
人は我が身を一番大切にいたします。そんな私たちに上人は、「多くの者に対して広く深重の大悲をおこせ」とお勧めになります。なぜでしょう・・・。それは、輪廻の苦悩から脱して仏と成るためです。近くは恩愛ある父母の救済、遠くは一切衆生を悉く救い尽くすという大慈悲の実践は、我愛のために輪廻する私たちを智慧と慈悲とが円満成就した仏陀の境地に至らしめるのです。本来的に智慧と慈悲は表裏一体のもので、智慧が育てば苦悩する衆生の姿が見えるようになり、慈悲心が起こります。また、慈悲心が現れれば「いのち」をありのままに見る智慧も磨かれます。ですから仏陀は、ありとあらゆる「いのち」 を慈しめ悲しめと教えられるのですが、私たち凡夫にはなかなかこれが実行できません。そこで、まず恩愛ある身近なものに向けて大慈悲心をおこせと上人はおっしゃったのです。なぜに私たちは生死苦悩の世界を輪廻するのでしょうか。これについて上人は『心要鈔』二利門の冒頭で、「生死の相続することは惑と業と苦とによる」と明言しておられます。惑とは煩悩のこと、業とは煩悩による行為のこと、苦とはその結果として受ける境涯のことですが、ここでも上人は「惑業苦」によって臨終時の重要性を示唆しておられます(臨終正念については第二話をご覧下さい)。すなわち、まことのことに暗い心(無明=愚癡)のままに日暮らしを送る私たちは、その行為によって次の世に生まれる迷いのタネ(種子=果を生じる力能)を造ってしまい、これが死の間際の貪愛によって潤され、新たな苦悩の「いのち」を結ぶと、上人はおっしゃられるのです。こうした輪廻の軛から脱する方法が、他ならぬ智慧と慈悲とを錬磨する菩薩行でした。ことに上人は、慈悲行の実践こそが菩薩行の要であると考えておられました。そこで、『心要鈔』では『大乗荘厳経論』に出る「菩薩は衆生を愛念すること骨髄に徹するほどである」という文章を示され、菩薩の行の本質は大悲行にあると述べられました。同様のことが『観音講式』にも述べられており、そこでは『瑜伽論』に出る「菩薩は大悲を本質とする」という一文を引いておられます。ですから、上人に「大悲の実践こそが菩薩行の要である」という強い思いのおありになったことは明白です。そして、この心(慈悲心)を発すにあたって、「父母の恩を思え」とおっしゃるのです。上人は『心地観経』に出る「世の人が造る罪はすべて子のためであり、この罪のために人は三途(地獄・餓鬼・畜生)に堕ちて長く苦を受けるのだ」とある一節に深く心を留めておられたことも『心要鈔』の文から察することができます。それが猛火の中で焼かれる「恩愛の者の言葉」となって示されたのでしょう。
まさしく菩薩の実践は大悲行に尽きる。これが上人の信念でした。これほどに明白に、自己を含む多くの者たちの進むべき道をご教示下さった上人でしたが、しかし上人はここで激しく悩まれます。はたして自分のような愚かな凡夫に、菩薩の道を歩むことができるのであろうかと。その悲嘆の深刻さについては次回、稿をかえてお話をさせていただきましょう。
関連情報
- - 関連リンクNo.16|解脱上人小話 第一話『解脱上人 観音に帰依なさる』
- No.18|解脱上人小話 第二話『解脱上人 臨終の式を厳修なさる』
- No.19|解脱上人小話 第三話『解脱上人 浄土を願生なさる』