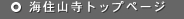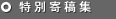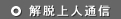���W�R���e���c�ꗗ
���W�R���e���c�ꗗ
�C�Z�R���g�b�v�y�[�W��
- ��E��l���W
- ��E��l��e�W�ꗗ
- ��E��l��e�W No.19
��E��l���b ��O�b�w��E��l�@��y���萶�Ȃ���x�b�� �~暁i���J��w�����j
�h���̋@���ɂ���Ă��łɏ㐶�𐋂��B�������@���Đ{�炭���ʂ� �i�ނׂ��B�������h�A�����ɗ��d���A�Z�s���n�A�Q�����i���A���� �ԉ��̕���ɏ���A�X������o�̑������ׂ��B
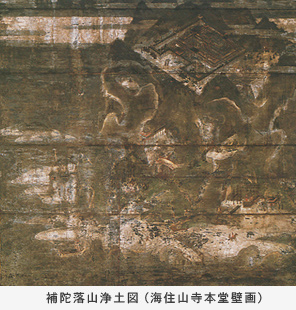 �@��̕��͂́A��E��l���������ɂȂ����w���Ӎu���x�̈�߂ł��B�����ł͏�y�ւ̉�
�������߂܂����A�Ȃ��Ɏ������͏�y�ɐ��܂��K�v������̂ł��傤���B���̓_�ɂ�
�ď�l�͏�̂悤�ɁA��y�ɐ��܂��Ε��ɐe���������A���������Ƃ��ł��邩���
����Ƃ������Ⴂ�܂����B���͎߉ޕ��̂悤�ȕ����܂̂���������Ȃ���������ł���
��A���ځA���ɋ���������ďC�s���邱�ƂȂǂł��܂���B�Ƃ��낪�A��y�ɐ��܂���
���ꂪ�\�ƂȂ�A���₩�ɏC�s��i�߂邱�Ƃɂ���āA�\�Z�E�\�s�E�\����E�\�n�Ƃ�
����F�̊K������X�Ə���A���ɕ��Ɛ��邱�Ƃ��ł���Ƃ����܂��B�����ɏ�l�́A��
���ȈӋ`�������o����Ă������Ƃ��A��̕��ɂ���Ēm���܂��B
�@��̕��͂́A��E��l���������ɂȂ����w���Ӎu���x�̈�߂ł��B�����ł͏�y�ւ̉�
�������߂܂����A�Ȃ��Ɏ������͏�y�ɐ��܂��K�v������̂ł��傤���B���̓_�ɂ�
�ď�l�͏�̂悤�ɁA��y�ɐ��܂��Ε��ɐe���������A���������Ƃ��ł��邩���
����Ƃ������Ⴂ�܂����B���͎߉ޕ��̂悤�ȕ����܂̂���������Ȃ���������ł���
��A���ځA���ɋ���������ďC�s���邱�ƂȂǂł��܂���B�Ƃ��낪�A��y�ɐ��܂���
���ꂪ�\�ƂȂ�A���₩�ɏC�s��i�߂邱�Ƃɂ���āA�\�Z�E�\�s�E�\����E�\�n�Ƃ�
����F�̊K������X�Ə���A���ɕ��Ɛ��邱�Ƃ��ł���Ƃ����܂��B�����ɏ�l�́A��
���ȈӋ`�������o����Ă������Ƃ��A��̕��ɂ���Ēm���܂��B�ŋ߂́u�قƂ��v�Ƃ����Ɓu���l�v��A�z�Ȃ�����������悤�ł����A�{���͐^�� �ɂ߂��߂����ҁi���Ɂj�̂��Ƃ������A��̔ϔY��f���s�����Đ�ΓI�Ȉ��炬�̋��n �Ɏ���ꂽ�������̗��z�I���݂��u�قƂ��v�Ƃ����̂ł��B�������A���j��̗B��̕��� �ł���߉ޖ������łȂ����Ă��炷�ł�1500�N���܂肪�o�߂��A�������ł�����ӂ� �o���Ȃ���܂łɂ͂܂�56��7000���N���̍Ό���������Ƃ����F�����A��l�����߂Ƃ��� �����̐l�X�ɋ��ʂ��Ă���܂����B
�@���̂悤�Ȓ��A��l�͓����A�u���Ԃ̕����v�ɂ��������Ĉ���ɕ��̏�y�ɐ��܂ꂽ�� �Ɗ���܂����B�Ƃ��낪�A����ɕ��̏�y�͂��܂�ɂ����ꂽ��y�ł���A�ꈢ�m�_�� ���̏C�s��ς\�n�̈ʂ̕�F�݂̂����߂ĉ������Ƃ̂ł��鐢�E�ł���Ƃ��m��ɂ� ��ƁA�u�U���v���l���Ă�ނȂ��f�O�Ȃ����܂����B�ł́A�ꈢ�m�_���Ƃ͂ǂ�قǂ̎� �ԂȂ̂ł��傤���B���ɂ��ĊH�q���Ƃ�����g������܂����A����ɂ��Ǝl�\������ �i���{���̈ꗢ�͖�S�q�j���̑傫�ȓ��ꕨ�ɊH�q���i�P�`�Q�o�j����t�ɂ��āA�O�N�� �ꗱ����菜���Ă����ċ�ɂȂ��Ă��܂����Ԃ��ꍅ�Ƃ����̂������ł��B�܂��A���m �_�Ƃ́u�����v�Ƃ���܂�����{���́u��������Ȃ��v�Ƃ����Ӗ��Ȃ̂ł����A���� �P�ʂƂ��Ă��O���T�U�ӂ����c��Ȑ��ʂɂ��Ă��܂����B�ł�����A�ꈢ�m�_���ɂ� ����Ԓ����Ԃ̏C�s�Ƃ����̂́A�������̈ꐶ�𐔂�����Ȃ��قǐςݏグ�Ă����Ȃ��� ���B�ł��Ȃ����̂ł���Ƃ������ƂɂȂ�܂��B
�@�����ŁA�u��v�̖}�v�v�Ƃ������o�̂�������l�͈���ɕ��̏�y���萶���邱�Ƃ�� �X�̊�]�Ƃ��Ă��������u����A���ɖ��ӕ�F�����݂܂��܂������V�ɏ㐶���邱�� ������܂����B��l�́u���ӂ͕�F�ƌ��Ȃ���Ă��邪�{�̂͂��łɕ��ł��邩�犕�� �V����y�ł���v�Ɣ��f�Ȃ����܂����B�����V�Ƃ����V�E�́A���������Z�܂����E�i�O�k�j �̏��ɂ���Ƃ��납��A�����ɐ��܂�邱�Ƃ��u�㐶�v�ƌĂяK�킵�Ă���܂����B�� �l�͛O�k���E�̖{�t�ł���߉ޔ@���Ɩ��ӂ���̂̑��݂ƌ��Ă����܂�������A��l�� ���ӐM�̔w��ɂ͋��łȎ߉ސM����ɂ���܂����B���������āA���̍��̏�l�̐M�� �͂��łɁA�߉ށE��ɁE���ӂ𒆊j�Ƃ��镡���^�M�i���ɖ�t�E�n���E�ω��E�t������ �Ȃǂ��܂ށj�ł���A���̔�d����ɂ�����ӂɈڂ����̂���l�́u�����萶�v�̂���� �ł������ƍl���邱�Ƃ��ł��܂��B�ł�����A����ȍ~����l�́A�����Έ���ɕ��ɑ� �������̏�𐏏��ɂ������ɂȂ�܂����A���������̍�����l�̐M�̒��S�͖��炩 �ɖ��ӂɈڂ�A������y�ւ̏㐶���Ӌ������悤�ɂȂ�܂����B
�@ ��y�@�\�\�\�\�@�B���̌��t�ɂ͖{���I�ɁA�ϔY���q��𗣂ꂽ���炩�Ȑ��E�Ƃ����Ӗ����� ��܂��B�B���̋����ɂ��A�^���̏�y�͌����J�������ɂ̑O�ɂ̂�������̂� ����A�O���������ׂ���y�͔@���̑厜�߂ɂ���ċ���ꂽ�u���̂��́v�ł���Ɛ��� ����Ă܂���܂����B�����āA�������̂��߂ɉ��ׂ��ꂽ��y��傫������p�y�i��y�j �ƕω��y�i���y�j�̓��ɕ����A��y�͏\�n�̈ʂɎ��������ꂽ��F�݂̂ɑ��Ď����� �ꂽ��y�A���y�͏\�n�̈ʂɎ���܂ł̕�F��}�v�̂��߂Ɏ����ꂽ���y�ł���Ƃ��܂� ���B�O�҂̏ے��I���݂�����ɕ��̋Ɋy��y�ł���A��҂ɂ͖��ӂ̊�����y��ω��̕� �ɗ���y�Ȃǂ�����܂��B
�@ ��l�̊����萶�̎v���́A���b�ł��b�����������N�i1199�j�́u�ՏI�̎��v�̋L�q�� ������܂��̂ŁA���̍��܂ł͖��ӐM�����S�I�ʒu���߂Ă������Ǝv���܂��B�Ƃ� �낪�A���厛�Ŕ��������w�ϐ�����F�������x�ɂȂ�ƁA�ω��M���O�ʂɎ������悤 �ɂȂ�܂��B�{���̖`���ŏ�l�́w���B���_�x�̕��������A�O���ɂ́u���ɂ��Ĉ�ɑ����v ������Ɓu��ɂ��đ��ɑ����v������Ƃ����邱�Ƃ��w�E���A����Ɉ����̐[�����҂Ƃ� �Ď߉ށE���ӁE��ɂ̎O���Ɗω��E�n���E����̎O��F����������ŁA�u�߂ނׂ��͊ω� �̖{���Ȃ�v�Əq�ׂĂ�����̂ł��B���������āA���̍��̏�l�̐M�͎߉ށE���ӁE ��ɁE�ω��𒆊j�Ƃ���l�������^�ɕϗe���A���̔�d���ω��ɒu�����悤�ɂȂ��� �ƍl����ׂ��ł��傤�B�����āA���m���N�i1201�j�̌܌��A��l�́u���Ԓj�����̂��߂� �ʊ�������āv�O�i���́w�ω��u���x����܂����B���ڂ��ׂ��͂��̒��ɁA���Ԓj�� ���̂��߂ɒ������Ƃ��������łɁA�u��Ƌ��ɕ�F�������H����v�Ƃ����ω��̐��� ������Ă��邱�Ƃł��B���̂�����������O�N�i1209�j�̘Z�i���́w�ω��u���x�ɔ� �f����Ă����̂ł���A���̓_�������l�̊ω��M���}�u���ォ��n�܂������̂ł��� ���Ƃ͊ԈႢ�Ȃ����̂Ǝv���܂��B�Ȃ��A���m���N�́w�ω��u���x�ł͖��炩�Ɏ߉ށE ���ӁE��ɁE�ω��̎l�������`�Ԃ��m�F�ł���̂ł����A�����O�N�́w�ω��u���x�ł͂� ��Ɏ߉ށE���ӁE�ω��̎O�������^�ɕϗe���܂��B�ł́A��ɂ��܂������������������� ���������ł͂Ȃ��A����̑O�N�Ɍ��q�M�L���ꂽ�w�ϐS�א���~�����x�ɂ́u�\�[���� ����M���v�Əq�ׂĂ��܂�����A���̎l���𒆊j�Ƃ��镡���^�M��������l�̐M�̂� ����ł������낤�Ǝv���܂��B�������ƁA�������͖}�v�ł�����ꈢ�m�_���̊Ԃ͈ꐢ �E�i��{��E�E��l�V���j�ɂ������܂ꂦ�܂���B�����ŁA�ՏI���Ɉꑸ�̏������肤�� �ł���A���̈ꑸ�̏�������ɂ�����ӂ����Ċω��ւƈڂ����̂��A��l�̐M�̓����� �������Ƃ����Ă悢�ł��傤�B
�@ �Ȃ��A�������̏Z�܂����y��萼��̕��p�Ɋω��̕�ɗ��R������Ƃ����Ă���܂� ���A��́w�ω��u���x��ʂ��Č������A��l�͊ω��̕�ɗ��R���܂������₷����y �ł���Ɖ��߂���Ă������Ƃ��m���܂��B�����[�����Ƃł��B
�֘A���
- - �֘A�����NNo.16�b��E��l���b�@���b�w��E��l �ω��ɋA�˂Ȃ���x
- No.18�b��E��l���b�@���b�w��E��l�@�ՏI�̎������C�Ȃ���x
- No.21�b��E��l���b�@��l�b�w��E��l �n�������Ȃ���x