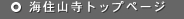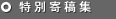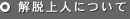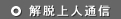海住山寺トップページへ
海住山寺所蔵の『解脱上人 大衣』・『慈心上人 七條』について
2.三衣(袈裟)に見られる戒律 [ I.三種賎 ] 戒律の観点から見た場合に袈裟について三種賎(体賎、色賎、刀賎)というものがある。 「体賎」は人々が捨てて顧みない布を使用できるものだけ選び、縫いあわせことによ って袈裟の材料とした。社会への執着を断つことであり、「糞掃衣」と呼称される由 縁である。「色賎」とは俗人が青、黒、白、赤、黄の五色の衣を着けるのに対して「壊色」と呼 ばれる不正色な袈裟をつけることは出家することで身も心も俗社会にとらわれない、 とするものである。
「刀賎」は大きな衣を得てそれを纏うのではなく、「截縷〔せつる」〕して 布を小さ く裁断し、はぎ合わせて方形の衣服をつくることであり、これによって執着ものとも 裁断することを意味している。
[ II.三衣(袈裟)の条数と用途 ] 目的や用途によって袈裟の条数が違うのだが、基本的にその条数はずべて奇数である。これば経典や仏法の教えは難解であるがゆえにすべて割り切ることができないからと言われている。またすべて、「長」という長い長方形の部分と「短」という短い長方形の部分の組み合わせにより構成されており、条数に応じて「長」の部分が増えていく。(「短」は常に一短のままである。)「長」は善を増長し、「短」は悪を滅するの意味とされ、条数が増えていくのは行位などによって徳が積まれていく、と解釈される。
次に名称とともに使用する用途と条数をあげた。
| 用途 | 条数 |
|---|---|
| 安陀会(五条) 旅行用、室内着、作務服 | 一長一短 |
| 鬱多羅僧(七条) 礼拝、読経、斎食、講説などの場合。 | 二長一短(両長一短) |
| 僧伽梨(大衣) | 礼服に相当する。晴れ着。 入王宮聚楽衣 、(宮中参内) |
| 九条、十一条、十三条 | 二長一短(両長一短) |
| 十五条、十七条、十九条 | 三長一短 |
| 二十一条、二十三条、二十五条 | 四長一短 |
[ III.三衣(袈裟)の各部の名称と田相の作り方 ] 三衣(袈裟)は「福田衣」と呼ばれ、衆生(田)に福(水)をもたらすためのもの、とされている。
| 葉 | 袈裟の田相でいえば、「あぜみち」の部分にあたる。 |
|---|---|
| 条 | 田の部分で縦に一列になっている部分をいう。 |
| 甲 | それぞれの田の部分。 |
| 縁 | 袈裟の四方をめぐる狭い布の部分をいう。 |
| 鉤紐、台座 | 袈裟を身に着けておくためのひも。紐をつける部分の補強の布片を台座という。四分律には場所は明記されない。 |
| 角牒 | 四隅にある小さな四角形の布。 |
| i 割截(かっせつ) | 衣片を縫い合わせることによって一つの大きな袈裟を作ることができる。「刀賎」に適う最も基本的な作り方である。 |
|---|---|
| ii ゼッチョウ | 大きな布地に小さな葉片を乗せて縫いつけていく。 |
| iii ショウヨウ | 一枚の布を折りたたむことによって葉の形を作ったもの。 |
[ Ⅳ.三衣(袈裟)の縫い方と日数 ] 直縫いした者がいたが、大衆の前で袈裟がほどけて大恥をかいたことがあったことに由来することから、還し縫いが原則である。
葉に関してはさまざまな縫い方があるが、まず、閉葉か開葉か、によって大きく分かれる。ここに戒律のよる大きな違いが見られる。四分律を提唱した南山大師道宣禅師(596~667)は閉葉(刺縫)することは縵衣と同じであると解釈する。『南海寄帰内法伝』の中で義浄(635~713)はインドでは刺縫し開葉しなかったが、中国では葉を縫わず開いており、有部律には開葉をいっていないと見なしている。 開葉については部族ごとの違いにより縫いに差があるとの見方があるが、いずれも丈夫にするためのものである、と考えられる。次に縫い方の別を示した。

イ 開葉
ロ 馬歯縫い
ハ 鳥足縫い
ニ 略馬歯縫い
ホ 編葉辺
(イ) 葉の部分縫い合わされておらず、いわゆる水通しがある場合が開葉である。
(ロ) 馬歯縫いは葉の部分が糸で馬の歯のように大きく象られている。
(ハ) 鳥足縫いは葉の部分が糸で鳥の足が二つ、三つと重ね、縫われている。
(ニ) 略馬歯縫い(一説には伝説鳥足という)とは葉の部分に「T」の文字の如く、
縫われている。
(ホ) 編葉辺はとは開葉部分を祭り縫いしていく縫い方である。
○安陀会(五条) → 二日
○鬱多羅僧(七条) → 四日 (有部律では二日)
◎僧伽梨(大衣) → 五日
[ Ⅴ.三衣の色相と染色 ] 袈裟 → 「濁」の音写語、袈裟色と訳されるべきである。 五方正色(青、黒、白、赤、黄)でない不正な色が、壊色(えじき 壊れた色)と解釈されるべきでそれぞれの律によって違いが見られる。
○四分律、五分律、摩訶僧祇律 → 青、黒、木蘭
○十誦律 → 青、泥、茜
○根本薩婆多律(有部律) → 青、泥、赤
それぞれ、壊色とすることを染浄といい、染浄のかわりに布片に点をつけて汚す点浄という方法もある。
『僧尼令』に僧侶の衣服として
木欄。青碧。皂。黄。及壊色等
と規定があるが、染色に関してはインドではミロバラン(和名 呵梨勒)の花や幼果を用いて染めていたようである。日本には薬草として持ち込まれ、正倉院に薬物として保存されている。 現在でも木欄色は多用されているが、実際の木欄色がどの色かは特定できない。これはミロバラン(和名 呵梨勒)を例にとると、媒染によって黄色から茶褐色あるいは黒まで染められる。要するに草木など同じ材料の染め粉であっても媒染によっても季節によっても異なることなどがあげられる。[ Ⅵ.三衣の衣材と衣量 ] ◎衣材
四分律では①絹、②木綿、③毛織、④亜麻、⑤野麻、⑥白羊毛、⑦鳥毛、⑧赤色羊毛、⑨灰色羊毛、⑩麻衣、の十種をあげている。 絹は蚕の命を害することによって得られるものであるから、袈裟の材料にしてはならないとした。絹布を用いるか否かの議論がなされるが南山大師道宣律師のみ絹布を認めなかったが糞掃衣の理屈からみた場合は成り立たない。よって、現在では絹、麻。木綿などが多用されている。
◎衣量
※肘(ちゅう)→ヒジを曲げた内側から指先までの長さ。
大衣 上品・・・竪三肘、横五肘 下品・・・竪二肘半、横四肘半
(中品は上品と下品の中間をとる)
七条 上品・・・竪三肘、横五肘 下品・・・竪二肘半、横四肘半
(中品は上品と下品の中間をとる)
五条 二種・・・(竪二肘、横五肘)、 (竪二肘、横四肘)
関連情報
- - 関連リンクNo.12|海住山寺蔵『解脱上人 大衣』・『慈心上人 七條』について その一
- No.40|海住山寺蔵『解脱上人 大衣』・『慈心上人 七條』について その三
- No.41|海住山寺蔵『解脱上人 大衣』・『慈心上人 七條』について その三