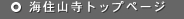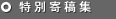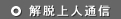海住山寺トップページへ
現光寺十一面観音坐像の造立背景をめぐって
現光寺は、海住山寺からみて南東約3km、木津川市加茂町大字北にある小さな寺院で、海住山寺が管理しています。その詳しい由緒は明らかでありませんが、元禄10年(1697)に再興された時、海住山寺縁起絵巻の詞書撰者である真敬法親王(興福寺一乗院門跡)が落成を賀したこと、正徳2年(1712)に貞慶上人の五百年忌に際して海住山寺の本堂開帳が行われた時、現光寺の住僧が参詣したことなどは、海住山寺とのつながりのもとで歩んできた歴史を物語っています。 ここでとりあげる木造十一面観音坐像(像高74.0cm、国指定重要文化財、以下「現光寺像」と略記します)は、その本尊として安置されてきました。作者や制作年代を語る史料は知られませんが、この像の造形自体がおおよそのことを語ってくれます。すなわち、頭部や胴部の張りのある肉づき、彫りが深く、一部に分岐も交える衣文など、その表現の特色に眼をとめれば、鎌倉時代前期の慶派仏師の作品であることが明らかになります。そして、腹部あたりを細く絞った胴体、左右に大きく張った両肘、膝の厚みを抑えた奥行きの深い両脚部、伸びやかな上半身、こうした肢体の構成が大きな空間を印象づけるといった造形性をとらえると、制作年代は13世紀第1四半期頃に絞り込むことができるでしょう。
ここでとりあげる木造十一面観音坐像(像高74.0cm、国指定重要文化財、以下「現光寺像」と略記します)は、その本尊として安置されてきました。作者や制作年代を語る史料は知られませんが、この像の造形自体がおおよそのことを語ってくれます。すなわち、頭部や胴部の張りのある肉づき、彫りが深く、一部に分岐も交える衣文など、その表現の特色に眼をとめれば、鎌倉時代前期の慶派仏師の作品であることが明らかになります。そして、腹部あたりを細く絞った胴体、左右に大きく張った両肘、膝の厚みを抑えた奥行きの深い両脚部、伸びやかな上半身、こうした肢体の構成が大きな空間を印象づけるといった造形性をとらえると、制作年代は13世紀第1四半期頃に絞り込むことができるでしょう。優れた出来映えはまた、像のつくられた背景へと関心をいざないます。それはどのように考えることができるでしょうか。
鎌倉前期までの十一面観音の造像例をみると、その大多数は立像で、現光寺像のように坐像で造立される例は少数派に属します。古代以来たくさんの十一面観音がつくられ信仰されてきた南都文化圏においてさえ、現光寺像は坐像の十一面観音として稀少な例といえ、前例となる像の存在も思い当たりません。どうやらこの点は、個別的・局地的な制作環境が関わっているように思われます。そこで思いあたるのは、制作年代が求められた13世紀第1四半期には、貞慶上人により海住山寺の復興がなされている事実です。そして貞慶上人の鼓吹した観音信仰には、以下に述べるごとく、坐像の十一面観音の造形を生み出す必然性があったと考えられるのです。
承元2年(1208)、貞慶上人は、笠置寺を離れて海住山寺に移り住みます。これ以降、かねて抱いていた観音信仰を一段と深めてゆくのですが、その特色として、観音の住処たる補陀落山への強い関心と、対象が十一面観音に特化していたことが挙げられます(貞慶上人の十一面観音信仰については、先にこの特集で苫米地誠一氏・井上一稔氏も言及されたところです)。もと本堂の壁画であった板絵《補陀落山浄土図》と《十一面観音来迎図》は、貞慶上人十三回忌に際して制作されたものの模写あるいは後身とされますが、貞慶上人の観音信仰の特色を象徴的に伝える遺品といえましょう。
補陀落山に寄せる貞慶上人の思いの深さは、次のような諸点から確かめられます。 まず、いまだ笠置寺に住していた建仁元年(1201)に撰述された二つの『観音講式』には、すでに補陀落山についての言及がみられます。そして海住山寺に移り住んだ翌年の承元3年(1209)に改めて撰述された『観音講式』(『値遇観音講式』)では、その大部分が補陀落山の具体的描写から構成されるまでに至っており、関心の深化が如実にあらわれています。そもそも「海住山寺」という寺名自体、補陀落山が海中にあるとされることを踏まえて貞慶上人が名づけたものでした(『明本抄日記』)。
建暦3年(1213)2月3日、貞慶上人は海住山寺において入滅しますが、その前月に記録された口述は、死の床にあった貞慶上人の抱いた補陀落山往生の願いを伝えています(『観心為清浄円明事』)。そして上人の没後、同胞や弟子たちのなかで、その願いは遂げられたと信じられたのでした(「貞慶十三回忌願文」、『華厳経観世音菩薩感応要文抄』)。
そして補陀落山における観音は、『華厳経』入法界品に「観自在菩薩於金剛宝石上結跏趺坐」と説かれ、貞慶上人の活躍する以前に南都で制作された《華厳五十五所絵(額装本)》(東大寺蔵)、東大寺旧蔵の《華厳五十五所絵巻》(藤田美術館蔵)でもそうであるように、基本的に坐った姿でイメージされていたのです。
このような、補陀落山へ寄せる深い関心と、十一面観音への対象の特化という貞慶上人の観音信仰の特色を踏まえると、貞慶上人の周辺において、補陀落山に坐す姿の十一面観音像が造立される必然性も明らかとなるでしょう。すなわち現光寺像は、海住山寺における貞慶上人の観音信仰の影響下で造立され、それゆえに坐像の十一面観音につくられたと考えられてくるのです。また、メトロポリタン美術館所蔵《十一面観音影向図》、根津美術館所蔵の《春日補陀落山曼荼羅図》は、いずれも補陀落山中に坐す十一面観音を主尊に描く鎌倉時代の作品ですが、前者は興福寺旧蔵と知られ、後者ともども貞慶上人所縁の観音信仰が思想的背景に想定されうるもので、この見方を傍証するように思われます。一方さかのぼれば、京都成相寺所蔵の《紺紙金泥十一面神呪心経》(平安後期)には、見返絵に補陀落山に坐す十一面観音が描かれており、図像的先行作例の存在を示唆するように思われるのです。
さらに制作背景が以上のように見出されるとすれば、現光寺像の制作年代の上限は、貞慶上人が海住山寺に移り住んだ承元2年(1208)に求められます。ただしその僅か5年後、貞慶上人が建暦3年(1213)2月3日に海住山寺において入寂すること、貞慶上人の観音信仰が没後に継承されゆく状況を思えば、貞慶上人の在世中に造像されたか否かは微妙なところとなってきます。
そこで注目されるのが、貞慶上人在世中から海住山寺の復興に尽力し、やがて第二世として伽藍の充実をすすめた覚真上人の存在です。現光寺像の推定制作時期は貞慶上人の没前没後にわたるのですが、いずれにせよ覚真上人の関与が考えられてよいでしょう。覚真上人の生涯については、先にこの特集で黒田彰子氏が在俗時代を浮き彫りにされていますが、興味深いことに、出家前の覚真上人は、興福寺復興造営の現場において、早くに慶派仏師一門に接しているのです(『玉葉』文治3年12月25日条・同4年6月18日条)。やがて覚真上人は、海住山寺のみならず興福寺や京都高山寺の復興造営にも尽力することになるのですが、いずれにおいても慶派仏師が参画していることは、現光寺像の作者とその背景を考える上でも手がかりとなるように思われます。
その造形表現から、13世紀第一四半期に慶派仏師により制作されたと考えられる現光寺本尊十一面観音坐像。ここでは、その制作環境が貞慶上人没前没後の海住山寺周辺に求められうることを述べてきました。そしてこの作業を通じて、覚真上人の存在の重要性もまた浮かび上がってくるように思われます。そういえば、先にこの特集で岩田茂樹氏が詳論された四天王立像は、貞慶上人入滅翌年に成った五重塔の安置像と考えられていますが、腰を絞って上半身の伸びやかなプロポーションには、現光寺像に一脈通じる造形性がうかがえないでしょうか。
なお最近、現光寺に伝世した木造四天王立像が、鎌倉時代前期における慶派仏師の作品として評価され、2007年、奈良国立博物館の平常展で初めて公開されました。その制作背景や十一面観音坐像との関係如何は目下明らかでありませんが、覚真上人時代の造営活動の所産と考えられうるかもしれません。今後の研究が待たれます。
関連情報
- - 参考文献 杉崎貴英「木津川市現光寺十一面観音坐像小考―海住山寺・解脱房貞慶・補陀落山浄土信仰・慈心房覚真―」
(『文化史学』第63号、2007年11月)